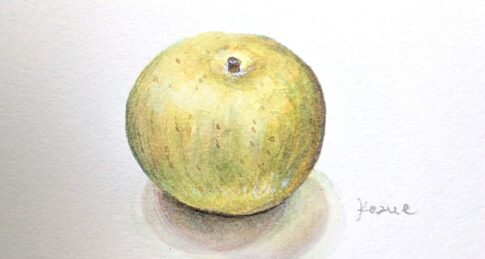透明水彩絵の具を使って絵を描いています。
ところで、皆さんは水彩画と言えばどんな絵を思い浮かべるでしょうか?
風景画は水彩画と聞いたときに、初めに思い浮かべる絵の一つだと思います。
空や山、街並み、水辺など…水彩で描く風景画は、写真とはまた違った魅力があります。

実は私も風景画は苦手なんですよ。 でも、むしろ風景画こそ気軽に描くことができるんです。 大事なのは上手く描こうと思うのではなく、「いいな」と思う気持ちが大切なんですよ。
挑戦してみたいので、風景画を描くコツなどを教えてほしいです!
では、今回は、風景画の描き方の基本とコツを紹介したいと思います。
透明水彩で描く風景画の魅力と、初心者の方でも安心して楽しめる描き方のステップをやさしく解説していきます。
この記事が皆さんの水彩画を描き始める一歩になればうれしいです。
では、早速始めていきましょう!
風景画を透明水彩で描く4つの魅力!
旅先でふと目に留まった風景、夕暮れの空など、何気ない風景に心を動かされたことはありませんか?
「この瞬間を残したい!」と思って写真を撮ったのに、あとで見返すと「自分が見た風景はこれじゃない」とがっかりしてしまう。
私もそんな思いを何度もしてきました。
透明水彩で描く風景画は、そんな“感じたまま”の空気や光を、そっと紙の上にとどめてくれます。
ここでは、透明水彩だからこそ味わえる、風景画の魅力を4つに分けてご紹介します。
感じたままを「自分らしく」表現できる
 風景画は、技術よりも「感じたまま」を描くことが大切です。
風景画は、技術よりも「感じたまま」を描くことが大切です。
うまく描こうとするのではなく、自分自身が「描いてみたい」と感じたそのままの気持ちを大切にすることが、何よりの表現となります。
風景を描くことは、日常の中にある静かな感動に気づき、自分自身と向き合う時間でもあります。
写真では写しきれない「そのときの気持ち」を、透明水彩ならやさしく表現できます。
少ない道具で「気軽に」始められる

水彩画は必要な道具が少なく、絵の具・筆・パレット・水・スケッチブックがあればすぐに始められます。
道具がかさばらないため、バッグにひとまとめにしておけば、描きたいときにすぐ取り出すことができます。
旅先の風景や立ち寄ったカフェ、公園など、「いいな」と感じた瞬間、 現地ではラフにスケッチしておき、帰宅後にじっくりと色を重ねて仕上げるのもおすすめです。
「偶然の美しさ」を活かせる

水彩の魅力の一つが、にじみやぼかしなど、偶然が生む美しさです。
水をたっぷり使って描くと、絵の具が紙の上で自由に広がり、思いがけない形や色が生まれます。
計算では作れない偶然のにじみやぼかしが、風景に深みと動きを与えてくれます。
人の手では完全にコントロールできないその表現が、自然の力に近い…そう感じるのは、きっと私だけではないはずです。
透明感が生む「光」と「奥行き」を楽しめる
 透明水彩は、絵の具を重ねても下の色が透けて見えるのが特徴です。
透明水彩は、絵の具を重ねても下の色が透けて見えるのが特徴です。
この透明感のおかげで、光や空気の重なりが自然に表現でき、絵に「奥行き」や「深さ」がうまれます。
たとえば、空や水面に映る光の反射、木々の重なり合う緑など、透明感のある描写は、見る人の想像力をやさしく刺激してくれます。
また、春の朝の柔らかい光、夏の濃淡のある日差し、秋の夕暮れの澄んだ色合い、冬の雪が積もる街並みなど、季節や時間帯によって移ろう微妙な色の変化も、透明水彩ならではの繊細さで描くことができます。
水彩画と淡彩画の違い
水彩画に似た描き方があるのをご存じですか?
それは「淡彩画」と呼ばれる描き方です。
皆さんも一度は目にしたことがあるのではないでしょうか?
「淡水画と水彩画、何が違うの?同じじゃないの?」と私も最初はそう思っていました。
どちらも同じ水彩絵の具を使って描く方法ですが、実は明確な違いがあるんです。
今回は、その違いを簡単に紹介していきますね。
水彩画とは?
 私が主に描いているのは水彩画です。
私が主に描いているのは水彩画です。
水彩画は、ラフに下描きをした後丁寧に彩色を重ねて仕上げていく描き方です。
色が主役で、光や空気感、雰囲気を繊細に表現できるのが魅力です。
屋内や落ち着いた場所など、じっくり時間をかけて描けるときに向いています。
「描き込む楽しさ」を味わいたい人に特におすすめです。制作にはある程度の集中力と時間が必要ですが、そのぶん仕上がった作品は、深みのある印象的なものになります。
淡彩画とは?

淡彩画は、鉛筆やペンなどで丁寧にしっかり描いたスケッチに、最小限の色で彩色する描き方です。
線が主役で、色は補助的に使います。
短時間で描けるという利点があるため、特に時間の限られた野外スケッチに向いています。絵日記やスケッチジャーナル、記録などにも使われます。
初心者におすすめの風景モチーフとは?
水彩画におすすめの風景は、自分の心が動いた風景、好きな場所を描くのが一番です。
とはいえ、そう言われても何を描いたら良いのか迷ってしまいますよね。
そんな時は、水彩画ならではの「にじみ」や「ぼかし」が生きるモチーフから始めてみるのはいかがでしょうか?
初めは複雑すぎず、水彩画の表現が楽しめる風景から始めるのがいいと思います。
水彩画を始めたばかりの初心者の方でも描きやすく、楽しみながら取り決める風景モチーフを紹介します。
空と雲のある風景

青空や夕焼けと言った空の風景は、シンプルですが水彩らしいグラデーションやにじみが楽しめるおすすめのモチーフです。
形や色ががさまざまに変化する空や雲は、「正しく描く」よりも「感じたままを描く」ことができます。
また、雲の表現にはリフトオフ(筆やティッシュなどで色をふき取る技法)などの技法を使うこともでき、技術の習得にもつながります。
山や丘に続く小道

遠近法の練習にぴったりなのが、山や丘に続く小道の絵です。
道の幅がだんだん狭くなっていく様子を描くことで、自然に遠近感が生まれます。
また、奥にあるものをシンプルに、手前のもの(草木や、岩など)を細かく描くことでより奥行きのある風景画が仕上がります。
水辺の風景

池や川、田んぼなどの水面に映る風景は、水彩画の透明感やにじみの美しさが良く映えるテーマの一つです。
特に川は、奥へと細くなっていく流れを描くことで遠近感の練習にもなります。
また、水面に映り込む空や木々は、にじみやぼかしの技法を使って柔らかく表現することもできます。
木々や緑が広がる風景

草木などの緑が主役の風景は、色の重なりの表現にぴったりです。
たとえば、木々の木の葉の重なり合うい色合いや、森の中に差し込む光などは、水彩ならではの表現を生すことで、自然な美しさを描くことができます。
筆のタッチやにじみを上手く使えば、細かく描き込まなくても雰囲気のある作品に仕上がるのも魅力です。
どこから塗ったらいい?風景画の彩色の基本
ラフを描いたらいよいよ彩色です。でも、「どこから塗り始めたらいいの?」と迷うことはありませんか?
基本を押さえておくと、絵に深みが生まれ、自然な風景に仕上がります。
ここでは、特に押さえておきたいポイントを紹介します。
一番奥(空や遠景)から塗り始めよう

風景画では、まず空や遠くの山など、背景から塗り始めます。
広い面はにじみやグラデーションを使って、柔らかく大胆に塗るのがポイントです。
初めから濃い色で塗らず、薄い色から始めましょう。怖がらず大胆に挑戦してくださいね!
明るい色から順に塗り重ねよう

水彩は「明るい色→暗い色」の順で重ねていくことが鉄則です。
いきなり濃く塗ると修正が難しくなるので注意が必要です。
光の向きを意識しながら、明るい部分を残しつつ塗り進めましょう。
手前の風景は後から描こう

空などの背景が乾いたら、奥の風景から手前に向かって描いていきます。
細かい部分はまだ描き込まず、大まかな形や色の配置を意識してバランスを整えましょう。
仕上げに細部と陰影を描き込もう

仕上げに全体のバランスを見ながら、影や細部を描き加えます。
にじみやぼかしを活かすのも水彩画ならではの魅力です。
描き込みすぎず、余白を大切にすることもポイント。
もし、「もう少し描き足したほうが良いかな?」と思ったら、少し離れて全体を見てみるのもいいですよ。
失敗を恐れない!描き直し&修正のヒント
水彩画は「一度失敗したらやり直せない」と思われている方も多いのではないでしょうか?
そんなことはありません。確かに「修正する」というイメージが湧かないかもしれませんが、ちょっとしたコツで修正や調整が可能なんですよ^^
描いている間に「こうしたらよかった」や、「しまった!」と感じたときも、落胆しなくても大丈夫。
そんな時に使える、簡単なテクニックをいくつか紹介しますね。
リフトオフを活用する

絵の具を塗りすぎてしまったときや、「しまった!」と思ったとき、絵の具を薄くする方法があるんです。
その方法は「リフトオフ」という技法です。リフトオフとは、水を含んだ筆やティッシュで色をふき取る技法のことです。
自分の思った形でふき取りたい場合は筆で。
自然な感じで拭き取りたい場合は、ティッシュを軽く丸めてふき取るのがおすすめです。
この方法は、絵の具が乾いていない状態でも、乾いた状態でも使えますが、乾いてから行う方が、ふき取りたくない場所までふき取ってしまうことがないのでコントロールしやすいかなと思います。
私は、塗りすぎたときや、雲や光の表現をしたいときに使っています。
ただし、色を完全に消すことはできないので注意してくださいね。色を塗りたくない場合は、マスキングテープやマスキングインクを使うことをおすすめします。
マスキングテープ、マスキングインクを使う

最初から白く残したい場所や描き込みたくない場所は、マスキングテープやマスキングインクを使うと、塗りすぎやはみだしを防ぐ事が出来ます。
使う際の注意点は、絵の具やマスキングインクが完全に乾いてからはがすこと。乾ききっていないうちに剥がすと紙を傷めてしまい、せっかく描いた絵の美しさが損なわれてしまいます。
・・・という私も、乾くのを待ちきれずつい焦って剥がしてしまった経験が何度もあります。そのたびに絵が傷ついてしまい悲しい思いをしました。
マスキングを剥がすときは、絵がほぼ完成する直前の大切な場面。
だからこそ、最後まで丁寧に、ゆっくり気持ちを落ち着けて作業することが大切です。少しの手間と時間が、作品の仕上がりに大きな違いを生みます。
焦らずゆっくり楽しんで下さいね。
色を重ねて修正する

色が薄いと感じた時はもちろんのこと、一部の色だけ浮いているように見えるときも、重ね塗りは効果的です。
また、境目などあえて濃くしてメリハリを付けることもできます。
私は「全体的にまとまりがないな」と感じた時に、全体に薄い色を重ねることがあります。
そうすることで、色味に統一感が生まれ、落ち着いた仕上がりになるんです。
注意したいのは、必ずしっかり乾かしてから塗り重ねること。
乾かないうちに塗ってしまうと、にじみや濁りの原因になってしまいます。
また、紙の種類によっては毛羽立ちやすいものもあるので、やさしく、丁寧に塗り重ねてくださいね。
不透明水彩で加筆する

透明水彩絵の具では表現が難しいハイライトには、白の不透明水彩絵の具(ガッシュなど)で補う方法もあります。
例えば、光が当たっている部分や水面のきらめき、白い小さな花などに、ほんの少し白を加えると効果的です。
ただし、使いすぎると水彩画特有の透明感が失われてしまうので、控えめに使うのがポイントです。
描いた後にスキャンしてデジタル加工する

仕上げて水彩画をスキャンや撮影し、デジタル修正するという方法もあります。
デジタル修正をすることで、コントラストや色合いの調整はもちろん、小さなミスや汚れもきれいに直すことができます。
また、SNS投稿や、作品集の作成にも活用しやすくなります。
失敗作品がデジタル修正をすることで、立派な作品に生まれ変わることがあります。
トリミングや展示方法を工夫する

たとえば、額装の工夫や部分的に切り抜いて、見せたいところだけ見せるという方法はいかがでしょうか?
描いたところを全部見せる必要はありません。
また、切り取った部分をほかの作品の素材として使うこともできます。
時間が経つと好きになることも

「失敗したな」と感じても、最後まで描き続けてみてください。描いている途中は失敗だと思っていても、少し時間を置いて見返すと、印象が変わることがあります。
また、味わいを感じられるようになったり、作品の魅力が増すこともあるんです。
もちろん、反対のこともあるのですが…
でも、最後まで描くことによって、「なぜ失敗したのか」「どうしたら思った表現ができるのか」を考えるきっかけになります。
それは最後まで描いたから見えてくる景色です。
私自身、途中で投げ出さず最後まで描き上げたことで、たくさんの気付きがありました。
「失敗した」「いやだな」と考えながら描くと、その気持ちも絵に伝わってしまいます。
「失敗した=嫌だ」ではなく、「失敗した=じゃぁこれをどうやっておもしろくしてやろうか」という風に、楽しむ気持ちを忘れないでください。
失敗を恐れず、楽しんで描いてくださいね。描くことで、必ず成長していきますよ。
まとめ
まとめです。
今回は、水彩絵の具を使った風景画の描き方のコツとヒントをご紹介しました。
実は私、昔から風景画がちょっと苦手なんです。
というのも、私は細筆で色を何重にも重ねながら、じっくり描くのが好きだから^^
でも風景画では、細い筆よりも、思いきって大胆に筆を動かす描き方の方が合うことが多いんですよね。
とはいえ、透明水彩と風景画は本当に相性のよい組み合わせです。
にじみや色の重なり、透明感から生まれる光の表現など、自然の魅力を引き出すのにぴったりです。
そんな透明水彩の魅力を、存分に楽しめるのが風景画の面白さでもあります。
最初から「苦手かも」と構えずに、まずは空や雲、小道、水辺など、身近で描きやすいモチーフから気軽に始めてみてください。
うまく描けなくても大丈夫。失敗を重ねながら描いていくうちに、自分らしい表現が少しずつ見えてきます。
そして、描くことそのものがだんだん楽しくなってくるはずです。
大切なのは、途中でやめずに、最後まで描いてみること。
焦らず、気負わず、あなただけの風景を、あなたのペースで描いてみてくださいね。
以上、水彩作家Kozue でした。
また別の記事でお会いしましょう。